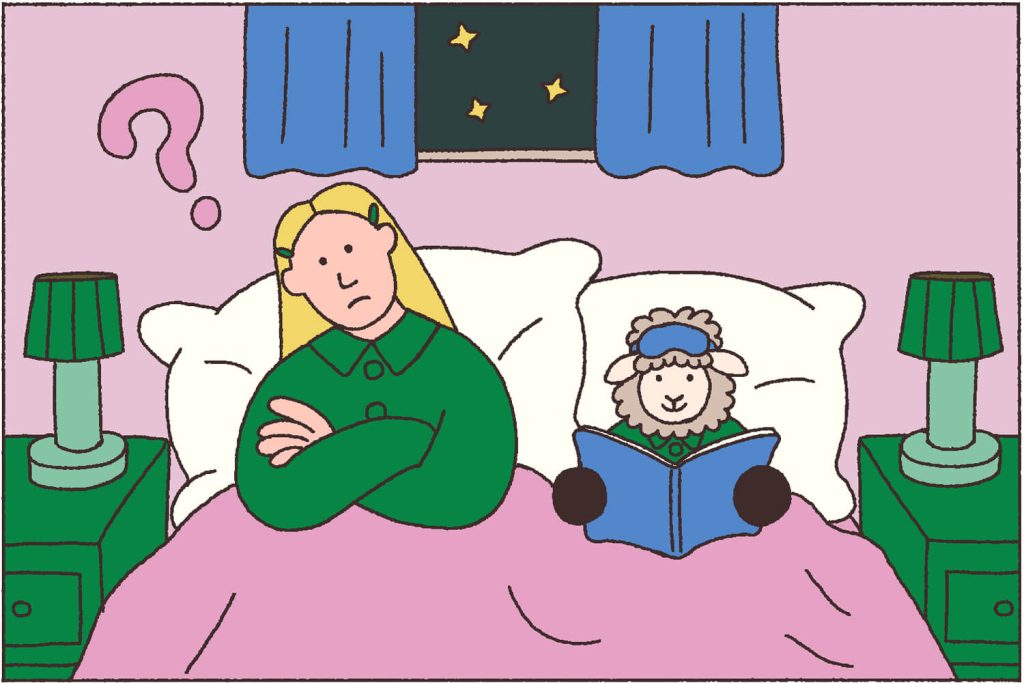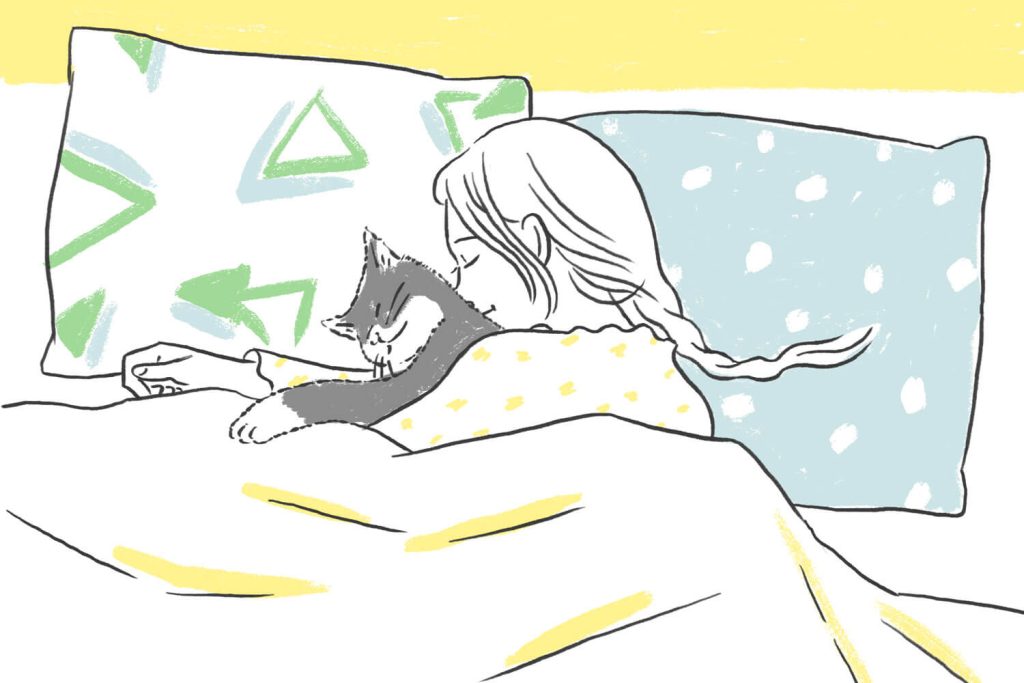加齢とともに増えるといわれている中途覚醒。じつは、年をとって眠りが浅くなることやトイレが近くなることだけでなく、ストレスや生活環境の変化など、身近なことが中途覚醒を引き起こしている場合もあり、子どもから大人まで幅広い年代にみられます。
本記事では、中途覚醒の原因を解説するとともに、予防のためにできることや、夜中に目が覚めて眠れなくなったときの対処法について実践的なアドバイスを紹介します。
- 教えてくれるのは…
-

- 渋井 佳代先生
- スリープクリニック銀座 院長
日本睡眠学会総合専門医。医学博士。信州大学医学部卒業後、東京都職員共済組合清瀬病院神経科、国立精神・神経センター精神保健研究所生理部研究員、同センター国府台病院精神科睡眠外来などを経て、平成19年よりスリープクリニック銀座に着任。睡眠障害、不眠、過眠、無呼吸症候群など睡眠にまつわる治療を行う。ベビーからシニアまで全年齢を対象とした睡眠医療に従事し、患者さんに寄り添った診察を心がけている。
[監修者]渋井 佳代先生:https://www.sleepmedicine-tokyo.com/clinic/ginza/
スリープクリニック銀座:https://www.sleepmedicine-tokyo.com
これって中途覚醒?見過ごせないケースの見分け方
中途覚醒とは、寝入ってから起床するまでの間に何度も目が覚めてしまい、その後寝つけなくなる状態をいいます。深夜に何度もトイレに行く(夜間頻尿)場合にも、中途覚醒が起きやすいです。
夜中に目が覚めたり、トイレに行ったりしてもすぐに寝つける人や、たまに眠れない日がある程度ならあまり心配はいりません。一方で、寝ているときに頻繁に起きることでつらいと感じている人や、日中の疲労感がとても強く居眠りをするような人は、中途覚醒による問題を抱えているかもしれません。
以下の項目に当てはまる場合には、根本的な原因解消に向けて、何らかの対処または治療が必要になることがあります。
中途覚醒の見過ごせないケース
□ 夜中に目が覚めると、その後寝るのに30分以上かかる
□ 中途覚醒が週に3回以上ある
□ 中途覚醒が3か月以上続いている
□ 起床時に疲れが取れていない、日中に調子が優れず困っている
(その原因が中途覚醒にあると思われる)
中途覚醒が起こりやすくなる主な原因
中途覚醒は、心身のストレス、加齢など、さまざまなことが原因で起こります。主な原因を紹介します。

1加齢による生理的変化
年齢を重ねると、体内時計や睡眠サイクルが乱れやすくなります。一般的には加齢とともに深い眠りが減ってくるため、中途覚醒が起こりやすくなります。深夜に何度もトイレに起きる場合には、「夜間頻尿」といって、尿や膀胱の病気に原因があることも考えられます。
2ストレスや不安
心配事や仕事のプレッシャーなどで緊張状態が続いているときや、転校・転職などの環境の変化がきっかけとなって眠りの質が悪くなり、中途覚醒が生じることがあります。うつ病などの精神疾患でも中途覚醒が見られることがあります。
3ライフステージや生活環境
妊娠・出産、育児、閉経など、とくに女性のライフステージには、生活環境やホルモンの変動が大きくなる時期があり、一時的に中途覚醒の悩みを抱えやすくなることも。子どもに夜泣きや睡眠障害があり、そうした環境から親が中途覚醒の悩みを抱えることもあります。
4カフェイン、アルコールの摂取
緑茶、コーヒーなどに含まれるカフェインやアルコールを摂取しすぎると、体が覚醒状態になりやすく、睡眠サイクルの乱れを引き起こします。睡眠中にトイレに頻繁に起きる原因にもなります。
5寝室の環境
寝室環境が暑すぎる、寒すぎる、不快など、気温や湿度、季節による日照時間の変化なども、睡眠に影響することがあります。
6睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群では、呼吸が一時的に停止するため、就寝中に目覚める原因になります。中年男性や肥満の人に多い病気といわれていますが、女性にもみられる病気です。また子どもでも、扁桃腺に問題がある場合に発症するケースがあります。
- 命に関わる「睡眠時無呼吸症候群」の原因と治療法
-
眠っているときに呼吸が止まってしまう「睡眠時無呼吸症候群」。発見の主な手がかりは「いびき」ですが、それ以外にも疲労感や倦怠感などさまざまな症状があり、放置してしまうと高血圧や心筋梗塞、脳梗塞等のリスクを上げる原因にもなる病気です。本記事では、睡眠時無呼吸症候群によって起こり得る危険や治療について解説します。https://helico.life/series/menshealthcare-suiminjimukokyu/
睡眠時のいびきを指摘されたことのある方や、日中に強い眠気を感じる方は、まずはこの記事を読んで、睡眠時無呼吸症候群について知っていきましょう。
7むずむず脚症候群
むずむず脚症候群は、じっとしているときや寝ているときに脚にむずむず感や不快感を覚える病気のことで、中途覚醒の原因にもなります。子どもから高齢者まで幅広い年代にみられ、その原因として鉄欠乏性貧血や糖尿病、末期腎不全などの病気が隠れていることがあります。妊婦のむずむず脚症候群は、鉄分不足が原因と考えられています。
どうしても眠れない夜の過ごし方
寝室で眠れない夜を過ごすと、脳が「寝室=眠れない場所」と記憶してしまうリスクがあります。眠れない夜はリビングなどに移動して、棚を片付けるなどの単純作業をしてみたり、温かい白湯を飲んだりしてから寝室に戻るようにしましょう。

重要なのは、とにかく頑張って寝ようとしないこと。「頑張ること=覚醒すること」なので、逆に目がさえてしまいます。自然な眠りを誘うには、「眠れない日もあるさ」と自分を許してあげるほうが効果的です。とくに年齢を重ねていくと、若い頃のように長く・深く眠れなくなるのはある程度仕方がありません。深夜にトイレに1度起きるくらいはよくあるので、気にしすぎないことも大切です。
睡眠時間を増やすために、早寝をするのは逆効果?
中途覚醒の対処法として、日中を活動的に過ごしつつ、睡眠時間はむしろ短く、濃くして深く眠る方が良いという考え方があります。夜中に起きるから早く寝ようとするのは、かえって浅い眠りを増やし、中途覚醒の原因になりかねないので注意しましょう。
生活に取り入れたい中途覚醒の予防法
中途覚醒の原因は多岐にわたるため、1つの対策でスッキリ解決することは難しいかもしれませんが、生活習慣の改善やセルフケアを試してみる価値はあります。
中途覚醒の予防法をいくつか紹介します。生活に取り入れやすいものから実践してみましょう。
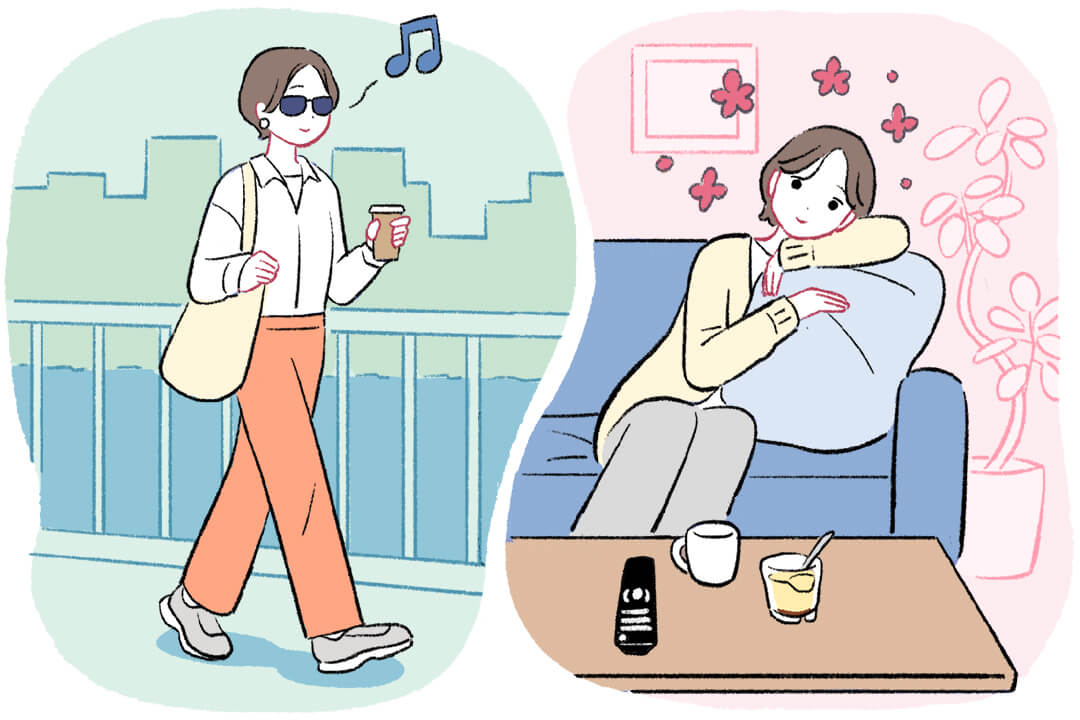
日中は活動的に過ごす
1日の終わりに心も体も適度に疲労している状態になることが、夜に深い眠りにつくポイントです。在宅ワークが多い人などは生活時間がルーズになりがちなので、日中は意識して体を動かしたり、外出したりしてみましょう。
カフェインやアルコール摂取を控える
カフェインやアルコールの分解には4〜5時間かかるといわれています。午後6時以降はカフェインを含む飲料を控える、お酒は休日に時間を早めて楽しむなど、工夫してみましょう。
寝室の環境を整える
寒い冬や猛暑が続く季節には、エアコンを活用して快適な室温・湿度を保ち、心地よく眠れる環境を整えましょう。
ぬるめのお湯にゆっくりつかり、寝る前にはリラックスして過ごす
夜の時間帯は、心身を休息状態に切り替えるためにも、交感神経を刺激しないようにします。ぬるめのお湯で入浴して深部体温を上げておくことや、リラックスして過ごすことが大切です。ホットアイマスクで目を休めたり、アロマを炊いて香りを楽しんだり、ストレッチをして体を気持ちよくほぐしたりするのもいいでしょう。ベッドでスマホが手放せない人は、スマホを遠くに置いて音だけで楽しむのも一案です。目を極力休ませると、リラックス感が高まるでしょう。
意識的にゴロゴロする時間をつくる
家事・育児・仕事に全力で向き合っていると、睡眠時間がいくら合っても足りずにイライラとストレスばかりが積み重なっていきます。家事を簡単にしたり、無理なら今日はできなくてもいいくらいの気持ちで、ときには自分を甘やかしましょう。朝ごはんはセルフサービスにするなど、上手にサボるのもおすすめです。余裕の持てる状況をどうしたらつくれるか、パートナーや子どもたちと話し合ってみるのも一案です。
困っているときや原因がわからないときは専門家に相談を
生活習慣を見直しても中途覚醒が改善せずに、日常生活に支障をきたしている場合には、医療機関を受診しましょう。何度も目覚めてしまう本当の原因や、自分に合った対処法を知るためにも、かかりつけ医や睡眠の専門医がいるクリニックで相談してみるといいでしょう。
いびきがひどい場合は、睡眠時無呼吸症候群が隠れているかもしれません。その際、寝ている間の様子を家族に動画で撮ってもらったり、アプリでいびきを録音したりすると、医師の診察の手掛かりになります。そのほか、夜間頻尿など主にトイレの悩みが大きいなら、泌尿器科を受診しましょう。
眠れないことに一人で悩まないで
「ぐっすり寝たいのに、夜中に目が覚めてしまう」「眠れないことにストレスを感じて余計に眠れない」など、中途覚醒の悩みは年代を問わず多くの人が抱えています。ベッドのなかではリラックスして休めるように、ここで紹介したセルフケアを参考にしてみてください。あまりにも大きないびきや、トイレがやたら近いといったことに思い当たるなら病気が隠れている可能性があります。その場合、治療で改善が期待できますので、一人で悩まずに受診を検討してみてください。