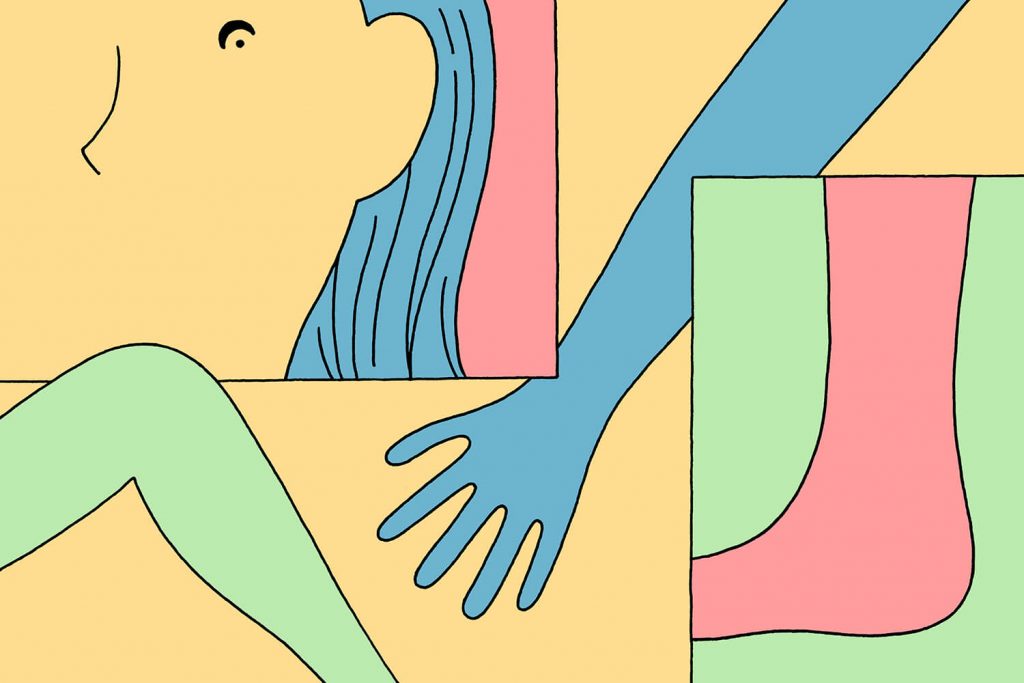マスクをつける機会が多くなりましたが、肌に接触して擦れることで、かゆくなったり、ヒリヒリしたりする人もいるのではないでしょうか。
今回は、マスクの着用によって引き起こされるさまざまな肌トラブルを知ったうえで、自分に合ったマスクの選び方や着用前のスキンケアなど、マスクと肌荒れに関する基礎知識をお届けします。
もう一度見直そう、マスクの正しいつけ方
マスクをつけていることによって起こる肌荒れの原因と対策について説明する前に、マスクは正しく着用できていますか? まずは正しいマスクのつけ方を確認しましょう。感染症を予防するためのマスクには、目的に合わせた装着の方法があります。市販のマスクには、外装のパッケージ部分に正しいマスクのつけ方が書いてある製品もありますので、参考にしてください。
- まず、鼻にあてて、あごをしっかりと覆うようにタテに伸ばします。鼻とあごの位置にフィットさせるためには、なるべくマスクの隅を持って調整しましょう。
- 隙間ができないようにマスクを顔にフィットさせて、耳にヒモをかけます。
- 耳にかけたヒモが緩すぎる場合には、耳にかけたヒモをクロスさせます。逆にヒモがきついときは、ヒモ部分に取り付けて後頭部や首にかけられるグッズを使用すると耳への負担がなくなります。
※ヒモが緩く、頬の部分に隙間がある「横スカ」状態は、感染症対策として誤ったつけ方なので注意しましょう。

正面からみると、しっかりと鼻のかたちにマスクが装着されており、あごまでマスクが覆われているつけ方がベスト(左)。横から見ると、マスクの頬にあたる部分がスカスカにならないようにフィットしている状態が理想(右)。
マスクの付け方と同様に注意したいのが外し方です。たとえば、のどが渇いて飲み物を少し飲みたい、というような場合には片側の耳にかけているヒモだけを外して飲むことをおすすめします。少しだけだからという感覚で口だけをカバーして鼻を出した「鼻マスク」、さらに鼻と口の両方を出した「顎マスク」の状態はやめましょう。「鼻マスク」では、自分の口から飛沫を飛ばすことは防げますが、他人の飛沫を鼻から吸ってしまう恐れがあります。「顎マスク」は、鼻と口のいずれもが無防備になってしまうことに加えて、顎の下に付いているかもしれないウイルスが下げたマスクの内側に付着して、口や鼻に入ってしまう可能性があります。また、マスク表面にもウイルスが付着している可能性があるので、表面をさわってマスクを上げ下げするのはNGです! さらに捨てるときにも、マスクを袋などに入れてからフタのついたゴミ箱に入れましょう。このような行動が、ウイルスの拡散を防ぐことになります。
マスクで気になる肌トラブルは、人によって違う?
正しくマスクをつけているつもりでも、マスクによる肌荒れは起こってしまいます。マスクによる肌トラブルの症状には、主に以下があげられます。いずれもマスクが触れている場所で起こりやすいといえます。
- かゆみ
- ニキビ
- 乾燥
- 唇の荒れ
- ざらつき
- ヒリヒリ感
- 赤み
マスクが擦れやすい頬や顎では、赤みや乾燥、ざらつきが起こりやすく、鼻の周囲から頬にかけてはニキビができて赤みが強くなる場合もあります。また、ゴムひもがあたる耳は、きつめのヒモだと食い込んで接触部分が痛くなる人もいます。そういったトラブルを起こさないように、肌とマスクの関係性を知ることが大切です。
マスクの種類によって異なる肌への負担とは?
じつは、マスクの種類によってマスクに覆われた部分の皮膚温度は異なります。たとえば肌に当たる部分がシルクのものでは、覆っている部分と、それ以外の部分の肌の温度差はほとんどありません。一方、不織布マスクでは、マスクそのものの温度は低いのですが、覆っている部分の肌は、温度だけでなく湿度も高くなるため、肌に負荷がかかり、外した直後に鼻の頭から頬にかけて赤みが強まることも。
また、不織布マスクは、外すと湿気が一気に蒸発するため、水分量と油分量が低下してしまいます。この状態は、皮膚のバリア機能が低下しやすい環境です。ここで適切な保湿ケアができなかった場合、マスクに覆われた部分の皮膚は乾燥しやすくなります。
マスクの影響などで肌が乾燥している場合は、マスクを着用する前に油分の多い保湿剤を使用して乾燥を予防します。一方、ニキビに悩んでいる人は、顔全体にローションタイプの保湿剤を使ったあと、ニキビ部分にはニキビ用の外用薬を使用します。乾燥部分には油分を、ニキビ部分にはローションを、という保湿剤の「使い分け」が大事。肌の状態を正確に把握したうえで、きめ細やかなスキンケアや治療を行っていかないと、状態を悪化させて治りが遅くなってしまいます。早めの対処を心がけていきましょう。
肌のことも考えたマスク選びとスキンケアのポイント
今後もしばらくはマスクを外せない生活が続くでしょう。そこで、トラブルを予防・軽減するための対策をご紹介します。
1サイズ
顔の大きさに合ったサイズを選んでください。マスクが大きすぎるとずれて摩擦が起こるだけでなく、ずれを調整するため、頻繁に手でマスクをさわってしまうことになります。マスクの表面にはウイルスが付着している可能性があるため、そこを無闇にさわってしまうと、せっかくマスクをしているのに、残念ながら感染症対策にはなりません。
一方、小さすぎるマスクでは圧迫による摩擦が大きくなり、肌に刺激を与えます。隙間をつくらないためだけでなく、肌への刺激をなるべく減らすためにもマスクは顔の大きさに合わせて適切なサイズを選ぶことが大切です。
2素材
不織布だとかゆくなるという方がいますが、ウレタン製マスクはデルタ株に対する性能が劣るとデータでわかっていますので、それを単独でつけることはおすすめできず、基本的には不織布のマスクが理想的です。「不織布マスク」とひとくちにいっても、最近ではさまざまな質感や形状のマスクが販売されています。いろいろ試してみて自分に合ったマスクを見つけましょう。
自分に合ったマスクがうまく見つけられなければ、一枚で使うことにこだわらず、マスクのなかにガーゼ(インナーマスク)などを入れたうえで使ってみることをおすすめします。肌があたるところには、抗菌処理済の肌に優しいシルク素材のマスクを使ってみるのも良いでしょう。また「ウレタンマスクの質感が好き」という場合には、ウレタンマスクの上に不織布マスクを重ねるのもおすすめです。
3マスク装着前のスキンケア
肌のトラブルを避けるために、マスク装着前のスキンケアは大切です。乾燥する人はしっかりと保湿を、ニキビができやすい人はノンコメドジェニック*を使って肌をケアしましょう。また、マスクはシミのもとになる紫外線を透過するので、紫外線対策は忘れずに!
*ノンコメドジェニックとは、コメド(面ぽう)を起こしにくいようにつくられている化粧品のことです。ニキビの原因となるアクネ菌の養分になりにくい成分で製造されているため、低刺激な化粧品といえます。
マスクは正しく使い、そのうえでさまざまな種類のマスクをTPOに合わせて使い分けられたら、お肌の調子も改善して気持ちも前向きになるはず。マスクをつけた生活、せっかくなら楽しみながら過ごしましょう!
- 教えてくれたのは・・・
-
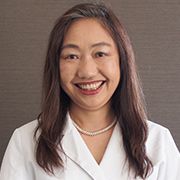
- 野村 有子先生
- 野村皮膚科医院 院長
皮膚科専門医。慶應義塾大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部皮膚科教室に入局。その後、神奈川県警友会けいゆう病院皮膚科に勤務し、アトピー性皮膚炎をはじめとするさまざまな皮膚の病気の診断、治療を行う。1998年に野村皮膚科医院を開業。2003年現在地に移転し、医院にアレルギー対応モデルルームやアレルギー対応カフェを併設。あらゆる皮膚疾患について丁寧に説明をし、治療からスキンケアにいたるまできめ細やかな指導を行っており、パッチテストや血液検査、皮膚組織検査などで病気の原因検索にも力を入れている。
日本皮膚科学会・日本臨床皮膚科学会・日本研究皮膚科学会・日本香粧品学会・日本皮膚アレルギー学会・日本アレルギー学会・ 日本抗加齢医学会・日本在宅医療連合学会・日本風工学会・神奈川県皮膚科医会・横浜市皮膚科医会に所属。